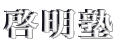実質全入校の受験対策
- 2023.02.20
実質全入校とは、実質倍率(受験者数/合格者数)が1.1倍を下回っている学校のことです。
定員割れ(志願者数/定員数が1.0倍以下)も同様に扱います。
実質全入校で「残念」にならないためには?
実質全入校は、手続き的なことを漏れなく行えば不合格にはなりません。
しかし逆に言えば、手続き的なことをしないと不合格になる可能性があります。
- 学校説明会で提示された「課題」を行っていない。
- 面接や志望理由書でアドミッションポリシーとは真逆のことをアピールした。
- 筆記テストの合格最低得点を満たしていない。
- 特別支援学級や長期欠席の場合に学校の受入可否確認を得ていない。
書類を出し忘れたとかの話じゃない!
受験を軽く考えている人は落とされるということです。
合格最低得点
筆記テストで一定以上の得点がとれていないと強制的に不合格にする「足切り点」です。
学校によって設定有無や公開有無が異なります。
非公開の場合は40点と考えておくのが無難です。
塾には通ったほうがいい?
結論的に言えば、絶対に通ったほうがいい。
正しい情報を得て慢心を防ぐために最もシンプルで確実な手段が受験塾に通うことです。
入試問題の難度以外のことは難関校も全入校も同じ
学力的な要求が低いので「安価な補習系や自立学習型でいいのでは?」と考える保護者が多いですが、その発想自体がすでに慢心ですし、正しくない情報に感化されている証です。
そういう人が必ず落ちるとは言いませんが、落ちる人は例外なくそういう人です。
個別指導塾を強く推奨
- 集団指導方式だと5年生後期からは学力格差の吸収が難しい。(オーバースペックな授業が多い)
- 6年後期の実戦演習は個別指導塾のほうが学習効率が良い。
- 難度が低いので自習教材で解決できる部分が多い。(週の回数は少なくていい)
- 夏休みと冬休みはコマ数を増やせば季節講習と同じ意味になる。
しっかりした「受験系個別指導塾」に月3~5回くらいのペースで通うのが推奨です。
既に自立学習型の塾を利用しているなら継続もあり
長期間の通塾で講師との信頼関係ができていいて、その講師が受験マネジメントができるなら継続もアリかもしれません。
入学前に基礎学力を固めておくほうがいい
多くの進路は学校推薦が主です。つまり校内成績が上位であるほど有利です。
合格難度に甘えずしっかり勉強しておけば、入学後に必ず有利になります。
入試順位の上位狙いは勧められない
実質全入校は入試選抜において「競争」は発生しません。ゆえに上位合格を目指したり他人と競うことに意味がありません。
自発的な学習の結果として高得点がとれるのは大変よいことですが、得点を上げるために理解が追い付かないことを詰め込むより基礎固めに注力するほうが有意義です。
そのためにもしっかりした塾に通っておく方がよいのですね。
塾は実質全入校をどう見ているのか?
格下に見られたりおざなりに扱われるような…
そうとも限りませんよ。
お買い得な学校
多くの人が学校選びで最初に見るのが「国公立や難関大学の合格実績」であることは否定できません。しかし県内は公立高校含めてABランク大学合格実績の大多数は塾ガチ勢か学校推薦によってつくられているのが現実です。
逆から見れば、Bランク以上に行きたいなら塾漬けになるか学校推薦の二択が静岡の高校生の現実です。
Bランク=偏差値55以上の大学です。全国準難関や地方有名私立大学が該当します。
「塾漬けはちょっと…」というなら推薦に強い学校を選ぶのが正解という考え方もあり、近年はBランクの推薦に強いにも関わらず合格難度が低い学校が注目されています。
静岡県にもそういう学校があるの?
かなりお買い得です。
但し恩恵を受けられるのは校内成績上位者のみです。
入学前に基礎学力をしっかり固めておくことがとても重要です。塾利用を推奨する理由はこのためでもあります。
実質全入の大学附属校に中学受験をして入るメリット
- 公立中学のお役所的価値観や高校入試に振り回されることを回避できる。
- 勉強が苦手な子でも比較的容易に「大学生」になれる。
- 中学進学以降は塾が不要なので、長い目で見ると学費総額は安くなることが多い。
消極的な…
そうとは言えないかもよ?
1クラス36人の小学校のクラスメイトの「6年後の進路」は・・・
| 36人 | 9人 | 4人 | A | 9/36 25% |
|---|---|---|---|---|
| 5人 | B | |||
| 9人 | 4人 | C | ||
| 5人 | D 12人 33% |
27/36 75% |
||
| 18人 | 7人 | C | ||
| 11人 | E |
| A | ABランク(偏差値55以上)の国公立や有名私立大学 |
|---|---|
| B | Cランク(偏差値50-55)の地方国公立文系や中堅私大 静大文系、県大、文芸大 |
| C | Dランク(偏差値45-50)の地方中堅私大 常葉(草薙C)、静理工 |
| D | 実質全入の地方私大や僻地公立大、短大、専門学校、予備校(浪人) |
| E | 就職 |
赤マスに該当する人にとっては物凄くメリットが大きいです。
改変履歴
- 【2023.04.27】雑多な記述を削除
- 【2023.02.14】初版