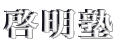学習塾の選び方
- 2023.02.20
小中高校生共通のものではなく、静岡県で中学受験をするときの塾の選び方です。
雑多になるので「塾が必要かどうか?」については論じません。

【鉄則】「受験対策塾」であること
学校は、その学校が想定する進路の選抜試験通過を到達目標とした授業計画や進路指導を行っています。
| 学校種別 | 想定進路 |
|---|---|
| 高校普通科 | 大学入学共通テスト5-7型 |
| 高校普通科選択制 | 大学入学共通テスト3/4型 指定校推薦、総合型選抜 |
| 技能総合校高校 | 総合型選抜、就職 |
| 公立中学校 | 所在地域の公立高校 |
| 中高一貫校 | (高校と同じ) |
| 私立小学校 | 接続する同一学校法人の中学校 |
| 公立小学校 | 学区の公立中学校 |
学校が想定している進路については黙っていても学校が提供してくれます。しかしそうでなければ必要なことは自己解決しなければなりません。
問題は、「小学校」は卒業後の進路に中学受験を想定していないことです。
次のような状況と同じです。
- 予備校に行っていない浪人生の大学受験
- 高認を経由する大学受験
- 高専や県外私立高を目指す中学生
中学受験は水先案内人が要るのですね。
受験塾とは「難しい勉強を教える塾」ではなく、水先案内の機能をもつ塾のことです。
受験情報の提供や学習計画の策定と必要教材の提案、合否判定を行えるのが「受験塾」です。
以降はもう少し具体的に挙げてみます。
学力に合わせる仕組みがあること
個人の能力、学習意欲、入塾時期、そしてパレート法則(働きアリの法則)によって、授業に適応できなくなる状況は非常に高い確率で発生します。あるいは当初の予定どおりに完走できる可能性は極めて低いともいえます。
「基本的に脱落する」というくらいの捉え方がちょうどいいです。
これを精神論でどうにかしようというのは現実味がありませんので、脱落を防いだり引き戻す仕組みが備わっている塾を選ぶことが重要です。
そしてその仕組みは単純に次の3種類しかありません。
- マンツーマン解説。つまり個別指導。
- 定期的な選抜テストによるクラス再編。入塾時選抜も含む。
- 難度別の選択式授業。つまりゼミ式。
集団指導塾にもAの個別指導はあるの?
「質問教室」とか「個別指導オプション」ですね。提携塾がある塾もあります。
過去問学習ができること
- 「試行」で時間を使う。(1科目で説明込み60分)
- 通しで解説すると通常設定の1コマでは収まらない。(算国2科目で4~5枠)
- 3~5年分を行う。
- 志望校によって様式が異なる。混成クラスでは生徒個々でやってる内容が違う。
- 過去問の出来具合は合否判定の基準になるため、出願前にある程度完成できる日程で進める必要がある。
過去問学習はこのような性質のため、塾によって実施方法に大きな違いがあります。
実施の有無だけでなく進め方の確認も必要
- 試行は日曜日の宿題→塾の時間に添削
- 1時限目に試行→2時限目に解説
- 週末や連休、冬休みの特別講習として一気に実施(1年分の試行と解説を1回4~5時間の講習で消化)
受験塾では過去問を上記いずれかの方法で行いますが、各方法は解説精度や費用にかなりの違いがあります。たとえば「C」は最も学習効率が良いですが、通常月謝の3~5倍の費用が追加でかかります。
このケースの場合、「追加講習は高いから要らない」とすると過去問学習はできないことになります。
確認必要っっっ!
過去問学習は自己解決ができない?
問題集としてみた過去問の解説書は簡素であり、答え合わせ程度にしか使えません。ゆえに講師による解説は必須です。
過去問学習の時期から塾をスタートするのは無理があります。
合否判定ができること
合判模試がしっかりしている都市圏では気にしなくてもいいと思います。しかし静岡には同一基準で複数校の合否目安を判定できる模試がありません。
ゆえに判定精度が低い塾では次のようなことが発生しやすくなります。
- 見込みがない学校に出願してしまう
- 見込みがあるのに回避してしまう
保険がかけられない状況が回避を助長する
静岡県は併願による「お守り」が付けにくい入試日程のため、安全重視傾向の判定をする傾向もあります。
安全校を確保した上で格上挑戦…は無いのか。
「危なそう」なのは実質全入校に誘導です。
まとめ:受験塾の必携三要素
- 学力に合わせた学習ができること
- 過去問の学習ができること
- 合否判定ができること
この3つを満たす塾は、決して多くはないです。
静岡に「受験塾」は少ない?
受験塾の数は地域の受験規模に比例します。この点で、静岡の受験規模は首都圏の1/15程度なので、当然ながら受験塾の数も少ないです。
| 首都圏 | 静岡県 | 静岡:首都圏比 | |
|---|---|---|---|
| 受験者数 | 50,000 | 3,000 | 1/17 |
| 対象学校数 | 234 | 33 | 1/14 |
| 東京23区 | 静岡県中部 | 比 | |
|---|---|---|---|
| 対象学校数 | 108 | 17 | 1/13 |
範囲を広げて探さなければ見つかるものも見つからないか。
改変履歴
- 【2023.02.20】刷新にあわせて文脈の見直し。
- 【2022.06.30】新装版に変更。会話型コメントを追加。
- 【2022.01.16】塾全体ではなく中学受験に限定した内容に改変
- 【2022.01.04】初版